火災保険料の値上げ
先日、火災保険を更新したのですが、ずいぶんと値上がりしています。
ほぼ5年ぶりの更新で、この間、2019年10月、2021年1月、2022年10月と値上がりが続いて、さらに2024年10月に最大の平均13%の値上げがあったようです。
ここ5年ほどで60%以上値上がりしていることになります。
火災保険値上げの理由
代理店の方に値上がりか続く理由を説明されました。
- 自然災害の増加
- 災害時の被害の激甚化
- 建物の老朽化の進行
- 再建築費、修理費の値上がり
どれも理由としては妥当で納得がいくものですが、こういった長期的な傾向も踏まえての保険料の設定なのではと思ってしまいます。
災害が増えたから保険料を値上げします、これが通用するなら私でも経営できます。
保険料を下げるための手段としての長期契約も、最大で5年になってしまっており、損害保険会社はリスクを取らなくなっています。
水災料率の細分化による負担の公平化
2024年10月の保険料の改定の目玉が水災料率の細分化です。
水災とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水による災害が原因で、建物や家財が所定の損害を受けた場合のことで、近年頻発・激甚化が著しい災害です。
これまでは保険料算出の基礎となる水災料率は全国一律でした。
実際のところ、水災に遭遇するリスクは場所によって相当に違うはずで、これが不公平感につながったり、水災保険への加入率の低下を招いていたとされます。
今回の変更で、リスクに応じて市区町村単位で5段階に料率が細分化されることになりました。

損害保険算出機構の資料より
最もリスクが少ないとされる1等地とリスクが大きいとされる5等地では約1.2倍の保険料の差が生じることになります。
決して小さくない差です。
ただ、問題は市町村単位で細分化される点です。
自分の家が地盤の強固な水害の心配のない土地に建っていても、その市町村全体で水災のリスクが大きければ5等地に指定されてしまいます。
逆に、頻繁に浸水するような場所に建っていても、その市町村全体ではリスクが小さいと判断されれば1等地ということになります。
ちょっと納得がいきません。
水災に関しては、どこが危険なのかもっと狭い範囲で指定できるはずです。
市町村単位などではなく、細かく指定してほしいものです。
ちなみに自分の住んでいる市町村が何等地に設定されているかは、損害保険料率算出機構の指定ページで調べることができます。
私の住む宮城県の場合、岩沼市、角田市、丸森町、涌谷町、美里町などが5等地に指定されています。
いずれも過去に河川の氾濫などがあった市町村です。
大崎市の一部でもひどい氾濫がよく起こっていますが、こちらは4等地です。
細分化がむしろ不公平感を広げているようにも感じられます。
水災のリスクから逃れる
私は水災から逃れるためには立地が全てだと思っています。
一度浸水したところは二度、三度と浸水します。
一度浸水した場所には家を建てられなくするほうが良いと思います。
幸いにも現時点において、我が家は水災のリスクはきわめて低いと考えられます。
良い場所に家を建てることができてよかったです。
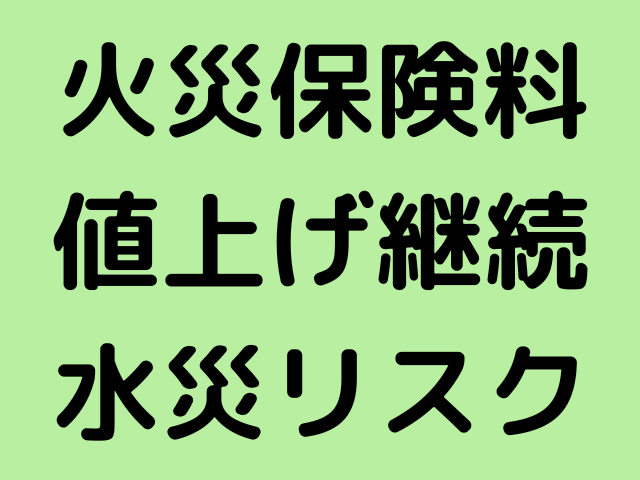
コメント